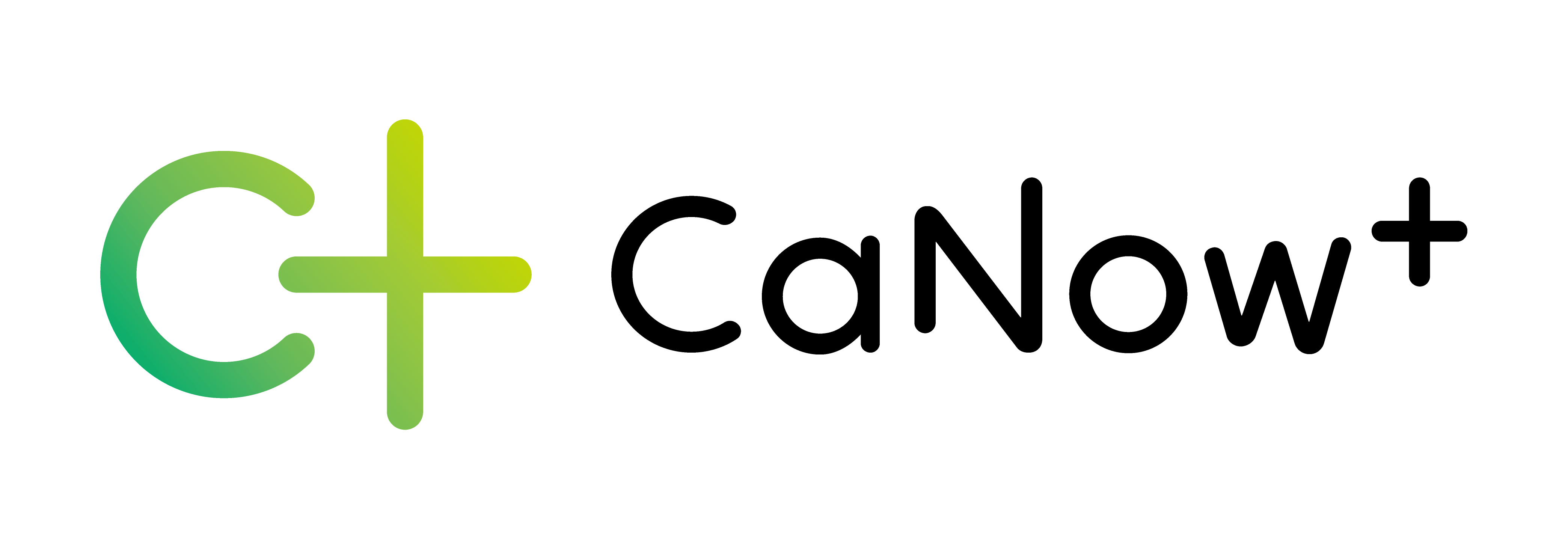インターネットの扉を開いた日から

―WEBサイトの歴史と、これからの希望をめぐる旅―
いま、私たちの生活の中で「WEBサイト」は当たり前の存在になっています。
スマートフォンを開けば、ニュースも、天気も、買い物も、調べものも、すべてがWEB上で完結します。
仕事でも、WEBサイトは情報提供の場を超えて、ビジネスの入口そのものとなっています。
私は、東京都立川市でWEBマーケティング支援を行っている「株式会社カナウプラス」の代表をしています。
働き盛りの40台半ばですが、私が社会に出た頃のインターネットは、まだ今のように手軽で身近なものではありませんでした。
時代は変わり、WEBは技術として成熟するだけでなく、社会のあらゆるシーンで欠かせない「インフラ」へと進化しました。
この変化の背景には、数えきれないほどの人や企業の挑戦と創造があります。
この記事では、WEBサイトの歴史をたどりながら、これまでの流れと、今後の可能性についてまとめてみたいと思います。
懐かしさと、少しの未来へのワクワクを感じていただけたら幸いです。
(今回はコラムページでありながらブログ風な発信になります☺)
■ インターネットの原点 ― 1969年、はじまりは軍事目的から
インターネットの原型は1969年、アメリカ国防総省の研究機関で開発された「ARPANET」にさかのぼります。
当初は研究機関間で安全にデータをやり取りするためのもので、一般市民が使うものではありませんでした。
それが学術機関に広まり、1980年代末には「ハイパーテキスト」という概念が登場。
リンクによって情報と情報をつなぐという発想は、まさに今のWEBの仕組みそのものです。
1991年、スイスのCERN(欧州原子核研究機構)で世界初のWEBページが公開されました。これが、今のWEBサイトの始まりです。
シンプルなテキストとリンクだけのものでしたが、それでも「どこにいても、誰でも、同じ情報を見られる」ことは革命的でした。
■ ホームページの登場 ― 情報発信のハードルが下がった
1995年、日本でWindows 95が発売されると、パソコンが急速に一般家庭に普及し、同時にインターネットへの接続が現実的なものとなりました。
この頃から、企業や個人が「ホームページ」を持つようになります。
初期のホームページは、文字と画像で構成されたシンプルなもので、どこか手づくり感のあるページが多かったように思います。
しかし、インターネットという新しい空間に、自分の情報を載せることができるという点で、非常に画期的でした。
企業も徐々に自社紹介のページを持ち始めますが、当初は「WEB名刺」といった印象でした。
まだ、集客や売上に直結する“動線”までは確立されておらず、パンフレットの延長線のような役割だったと記憶しています。
■ 2000年代 ― 検索エンジンとブログが文化をつくった
2000年代に入ると、Googleの登場によって、検索という行為がインターネットの中心になります。
あらゆるWEBサイトが、検索結果の上位を目指して競うようになり、「SEO(検索エンジン最適化)」という概念も広まりました。
同時に、ブログサービスの台頭により、誰もが簡単に自分のページを持てるようになります。
これは、情報発信のハードルを一気に下げ、ネット文化の多様性を生み出しました。
企業サイトも、商品紹介だけでなく、「企業としての考え」や「お客様の声」など、より人間味のある情報を掲載するようになり始めます。
【伝える】だけでなく、【つながる】ことが意識されはじめたのがこの時期です。
■ スマホの時代と、WEBの再定義
2010年以降は、スマートフォンの普及がWEBの在り方を大きく変えました。
「パソコンの前で見るもの」だったWEBが、「手のひらの中でいつでも使うもの」になったのです。
それに伴い、WEBサイトは「スマホ対応(レスポンシブデザイン)」が当たり前に。
文字のサイズ、画像の配置、ボタンの位置なども、使いやすさが重視されるようになりました。
また、SNSとの連携が強化され、WEBサイト単体ではなく「情報発信の中心点」としての役割が明確になります。
一方通行だったWEBは、ユーザーと企業が対話できる「場」へと変わったのです。
企業にとってのWEBサイトは、単なる情報掲載の場所ではなく、「顧客との関係性を築く装置」になりました。
■ コロナ禍で実感した、WEBが社会インフラであるという事実
2020年、新型コロナウイルスの世界的な流行により、私たちは突然、オンラインでの生活を余儀なくされました。
学校、行政、医療、買い物――あらゆる場面でWEBの存在がなければ社会が立ち行かなくなるという現実に直面しました。
WEBは、もはや選択肢のひとつではなく、「社会を動かすための基盤」になったのです。
このとき、多くの企業や個人が「WEBの力」を見直し、再投資を始めました。(どんな環境下でも働くWEBサイト)
事業の説明だけではなく、採用情報、理念、代表のメッセージなど、「信頼を育てる場」としての価値が再評価されています。
■ これからのWEBサイトに期待される役割(客観的な見方です)
今、私たちは新たな変革期に差しかかっています。
AIの活用、音声検索、ウェアラブルデバイスの進化――こうしたテクノロジーとWEBが融合することで、体験の質が変わり始めています。
WEBサイトは、次のような方向へと進んでいくでしょう。
- 「情報の一方通行」から「個別対応」へ
ユーザーの好みや状況に応じて内容が変わる、【動的なサイト】が一般的になるかもしれません。 - 「文字と画像」から「感覚の共有」へ
ARやVRなどを通じて、商品やサービスの【空気感】までWEBで体験できるように。 - 「利便性」から「信頼性・安心感」へ
選ばれるWEBサイトには、デザインや技術だけでなく、企業の姿勢や誠実さが求められるようになります。
◆ WEBの進化がひと目でわかる!
―WEBサイトとインターネットの年表―
| 年代 | 出来事・キーワード | 補足・背景 |
|---|---|---|
| 1969年 | ARPANET誕生 | 米国国防総省が開発した世界初のネットワーク。インターネットの始まり。 |
| 1989年 | WWW構想が発表される | ティム・バーナーズ=リーが「ハイパーテキストで情報をつなぐ」仕組みを提案。 |
| 1991年 | 世界初のWEBサイト公開 | CERN(欧州原子核研究機構)で情報共有を目的に公開。 |
| 1995年 | Windows 95発売、日本でインターネット普及へ | 一般家庭にパソコンが広まり、個人のホームページブームに。 |
| 2000年前後 | 検索エンジン・ブログ文化の成長 | Yahoo!やGoogleが台頭。個人が情報を発信できる土台が整う。 |
| 2004年 | Facebook、YouTubeなどSNS登場 | WEBが双方向の「つながる場」に進化。 |
| 2010年 | スマートフォン普及 | WEBが「いつでもどこでも使える」存在に。レスポンシブ対応が常識化。 |
| 2020年 | コロナ禍でWEBが生活インフラに | オンライン化が加速。教育・医療・行政までもWEBシフト。 |
| 2023年〜 | ChatGPTなど生成AI登場 | WEB体験が「人に寄り添う」フェーズへ。個別最適化が進行。 |
| 未来(予測) | WEB×AI×リアルの融合 | 音声・AR・ウェアラブル連携による「五感とWEBの統合」へ。 |
■ 株式会社カナウプラスとしての想い
株式会社カナウプラスは、東京都立川市から全国の皆様へWEBを活用したビジネス支援を行っています。
ただWEBサイトを「作る」のではなく、「伝える」「つながる」「育てる」ための支援を通じて、お客様と社会の未来を一緒に描いていきたいと考えています。
WEBサイトには、可能性があります。
それは、情報を届けるだけでなく、人を動かし、心を動かし、未来の価値を育てていく力です。
技術が進化しても、その本質は変わりません。
私たちはこれからも、WEBの力を信じ、活かし、必要とされる存在であり続けたいと願っています。(ご一読ありがとうございます)
著者:株式会社カナウプラス 代表
ウェブ解析士として、SEO対策・MEO対策・WEBサイト改善を専門に支援。
広告業界で培った分析力と、AIを活用したSEOメソッドにより、実店舗型ビジネスや専門業界の上位化を多数実現。